ロック史を体系的議論から解き放ちながら、サイケデリアの土着性とハードロックの非継承性を論ずる。主要1000タイトル、20年計画、週1回更新のプログ形式。
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「znr/barricade3(1975)rer znr1」 2009年1月18日 仏滅 全共闘忌
本日は40年前の東大安田講堂籠城戦の日であった。これに呼応したのか、ここ数日の間に民放およびNHKで安田講堂事件を振り返る番組みがなされた。民放ではドラマと実際の記録映像を交互に繰り出す仕組みであり、且つ官憲および学生両者の視点から描く試みに見えるがそれは無論形式上の事に過ぎず、結局は官憲権力側からの総括に過ぎないだろう。専ら官憲の反共視点から描かれた浅間山荘事件の映画などでも名を上げ、今もメディア等で反共の英雄と自他共に認められる官憲の佐々淳行役を、浅間山の映画では役所広司であったが今回の民放ドラマでは陣内孝則が演じていた。浅間映画での佐々は、庶民から限りなく遠い凶悪犯罪者どもと粛々と対決解決する冷静なる正義の警察官とその的確な指揮ぶり、として演じられ、籠城者の左翼の人々の背景思想については全く触れられもせぬ徹底的な無視が決め込まれ、露骨極まりない反共国策映画といっても過言ではない。一方このほどの民放安田ドラマにおける佐々は、かつてNHK大河ドラマ「太平記」でバサラ大名佐々木道誉を演じた陣内の、不逞な気骨すらない単なる下品なありようによって、国家権力を笠に着て正義を行おうとする出自の根源的な卑しさが露出する警察という人種のチンピラ犬ぶりが如実に表されており、佐々(陣内)が醜く口をゆがめて学生どもへの悪意を噴出させながら攻撃命令を下すごとに、制作者側(メディアと資本と国家)の意図に反したのかどうか分からぬが、警察の不動の正義を堂々と示す事にはならず、専ら陣内特有の演戯の醜さによって官憲の醜さをも露呈させるに至っていた。時折この佐々は、「学生をここまで追い詰めた社会が悪いかも」、とか、果ては、「このように弾圧されて、これ以降、学生に反骨の元気が無くなったらいやだな」、といった台詞を申し訳程度に棒読みしていた。敵に憐憫されるほど屈辱はなかろう。そしてその舌の根も乾かぬうちに喜び勇んで突撃命令を煽るのである。開いた口がふさがらない小生をさらに唖然とさせたのは、元学生運動家で籠城戦に参加していて今はなぜか東大の経済学教授の、過去を振り返るようなコメント、正確な言葉は忘れたが、大意としては、「まあ、あの頃は元気があった、熱に浮かされていた、今の学生も、38℃くらいの熱に浮かされるべきではないか、40℃では困るがな」、などとしゃあしゃあと転向発言するのである。転向は構わぬが、その転向の恥を持って生き続けなければならないというのが小生の思いではある。この恥は次代の新しい運動展開の原動力になるだろう。そして恥を生き続ける実践とは、メディアに利用されぬことではなかったか。ここまで来れば最早厚顔無恥の一言では納まれぬ、これほど怒りを通り越した衝撃は全く久方ぶりであった。この教授の発言、体制の許容範囲内におさまる若い連中のやんちゃぶりとその無自覚な媚びを可愛がるが、許容外の反権力活動は否定する、明白なる体制側意見であり、団塊にありがちな趣味の悪さを露見させた。だいたい、法律遵守しながら革命などできるか。この教授、および、陣内にああした台詞を言わせた制作者側は、大江健三郎の小説世界であれば、直接行動を辞さない左翼残党の総括部隊によって真っ先に半殺しの標的になるだろう。無論、小生はこの教授をよく存じ上げないし、それにテレビのやることだから、たとえこの教授がマルクス主義についての私観を捲くし立てたとしてもカットされる可能性大である。(東大にそんな教授がいるとは考えられぬが)
官憲が活動家を憐れんでいるような台詞を吐かせることで、運動の脅威をも体制に取り込んだことの既成事実を肯定し、かつ、実際にすっぽり体制に飲み込まれた(らしき)教授を出演させる。もし極左の人々が生き残っておれば、主義と言うよりも人間としての怒りに実直して、形振り構わず制作者に攻撃をしかけるだろう。しかし、こうした放送がされたということが、むしろ、この放送を見て怒りに駆られる極左など最早存在せぬと過信する体制の意図がうかがえるのであり、事実そうなのだろうと小生思う。勉強不足の連中に共産主義の要旨を説明しようともしない浅薄さでありながらも、一応、学生と官憲を平等に描こうとした番組意図が、その余裕が、反権力運動の終わりを一方的に宣告しており、歴史の年表に書き込んで過去に封印しようとしているのである。ただし、ドラマ中、講堂を取り巻く官憲の後ろで、老人が、旧帝大の戦争協力を声高に告発するシーンがあったが、辛うじて民放の良心をここに目撃した。
ただ、なぜ今頃メディアは学生運動を取り上げるのだろうかと考えた場合、やはり昨今の、資本主義批判に傾きつつある民衆の心情にあるのだろう。資本主義がおかしいから共産主義、というのも今となってはあまりに短絡ではあるが当然の成り行きではある、蟹工船は売れる、党員は増えてもいる。そうした社会情勢に呼応するようにしてメディアは過去の運動を取り上げるのであるが、その内容の多くは体制側であり、運動の無意味を暗に訴えるものであり、蒙昧な庶民に思想家=危険人物、という図を植えつけるのである。往時の左翼運動をよく知らぬ若い者らの、共産主義への淡い憧れを予防すべく、体制側は、運動の無意味さ、転向者の無恥の醜さを晒すのである。
そうはいってもNHK、元活動家の、それぞれのその後をじっくり追うルポ形式にて、どこまでも放送の中立への意志が見て取れた。指摘したいシーンは山ほどあったが、安田講堂事件の写真展なるものが最近開かれ、かつての闘士たちが運動を懐かしむために集うという、ある種の団塊特有の醜さが露呈する場面を挙げておきたい。また、元活動家の教授が、学生に鍋物を食わせながら、アジ演説を聞かせて感想させる場面があったのも興味深い。録音のアジ演説、早口すぎて小生には全く分からなかったが、学生にはその筆記資料もプリントしているようだ。距離を置く反応しかせぬ今時の学生。そういえば、今年早々に、NHKで、去年11月の東大駒場祭にて、学生らと、元全共闘の団塊らとのシンポジウムが開かれたのを放送していた。どういった議論が交わされたか、殆ど流されなかったが、キンキキッズと吉田拓郎とのフォークを介した結託、つまりキンキキッズの、吉田拓郎およびフォーク世代への媚び(近々きっちり書きます)、のような、最近の打たれ弱い若者に見られがちな団塊への無恥なる媚びでなければよいが、と願う。そういえば民放でもNHKでも、出てくるのは元活動家ばかりであった。恥を知る活動家は矢張り野に下りて草の根運動を着実に紡いでいるのか、いずれ日の目をみることを陰ながら願う。
さて、ZNRである。フランス。日本全共闘ではしきりに、インターナショナルを時に歌いながらも、世界の音楽手法の歴史から全く眼を背けたルサンチマンに無恥無自覚で何よりも音楽として退屈極まりないフォークソングを歌っていたようである。(ただ、メディアはロックを本性的に決して照らさぬので、ひょっとしたら全共闘でもロックされ、しかしメディアによって体制馴致のフォークにすり替えられたのかも知れぬが)しかし、1968年パリの5月革命では、バリケードの中でロックが奏された。(例えばその名も「コミンテルン」というバンドがバリケードでギグしていた)このアルバムの成立詳細はライナーを参照していただきたいが、当時のフレンチコミュニスト学生がアンガジュマン(政治参加)ロックしていた頃の生の音である。比べるのもおこがましいが和製フォークなどは全く話にならぬほどの、人間の音楽史を出来るだけ身に受けようとする気概のある音楽性である。最早、いわゆるブルース形式すら捨て去ったフリーインプロヴィゼーション作品である。拙い、幼稚ですらある爛漫な小声のキーボードが訥々しながら、凶暴むき出しのサックスが突出するも、あくまでも弱者の怒りを意地悪く剥きだす巧妙かつ意義深い音楽である。言語も英語、仏語、スペイン語、中国語とインターナショナル。どこまでもフリーにその辺の雑貨を叩いたり、ノイズや物音、自作楽器も当然やる知性。過去の音楽制度をしっかり見据えた上でそれへの反抗を試みるこうした音楽は、矢張り政治革命の本義にも適うだろう。(無論、ここまで書いておきながら今更であるが、ZNRの音楽は左翼の教条的解釈におさまるものではない。ただ音楽として注意深く聞くことが肝要)対して、和製フォークは、先述したようにその音楽形式への無自覚のため、体制馴致の音楽に過ぎない。よって、同じく革命を志しながら、日本全共闘とパリ5月では少なくとも音楽のレベルは歴然であるばかりか、革命の試みの結果にもそれは現れた。パリ5月では学生だけでなく労働者との共闘もあったことが一つの成功を導くが、安田事件では労働者を巻き込めなかったという挫折、運動の未成熟さは音楽に如実に現れているではないか、と下衆の勘ぐりしたくなる。フォークなどやっているから体制に飲まれるんだと野次されてもあながち野次には留まらないだろう、結局はそうした拙い音楽観が政治レベルでも露見してああした体たらくになると、少なくとも音楽の側面からは断言できる。ZNRはレコメンディッドレーベルの日本支部「ロクス・ソルス」で買えます。
joseph racaille :acoustic and electric guitar, ARP2600, voice
hector zazou :ARP2600, VCS3, bass, violin
patorick portella :bass clarinet, clarinet
andre jaume :soprano and tenor sax
david rueff :alto sax and flute
haevey neneux :guitar
gilly bell :ARP2600&c
fernand d'arles :percussion
大河ドラマ「天地人」で、上杉軍が山脈の尾根を行軍するに魅せられて、来週からしばらくの間、ザッパの音楽山脈を論じます。2回ザッパのアルバム、1回その他のアルバム、という形式で連載します。この山脈を超えずして、ロックは語れぬ。今まで逃げてきたが、時が来たのである。
「duncan browne/give me take you(1968)vicp-61245 」2009年1月11日 先負 曇鈍
左の日本焼物紀行の中に、「弘法市紀行~命日が縁日になった男~」をUPしました。今すぐクリックしてくだされ。
さて、日曜日午前1時過ぎ、犬のように酒を舐めながら、音は消してカウントダウンTVを血走った眼でねめつけるようにして漫然と憤然と見続けるのは、人生における軽薄なる退廃の極みであろう。取り返しのつかぬ無駄な時間である。嘆いても後の祭りであった。たとえ猪口が備前、徳利も備前(義父の御手製)、酒も備前の、雄町の泉、であっても。
さておき、ダンカン・ブラウンである。英国。7年前ぐらいだろうか、そのジャケットからプログレだろうと思って購入した、いわゆるジャケ買いであるが、中味はクラシカルな英国フォーク、トラッドを色濃く基調にした物寂しいポップ作品であった。ギターがポロポロ鳴り、おとなしげな男が小さく呟いている。全く情報を得てない中で買ったものであるが、この人物、70年代終りの英国モダンポップ期においてロキシーミュージックや10CC、XTCといった奇怪なバンドに比肩し得た、メトロというデュオバンドの片割れであった。当時の、短命をよしとしたパンクバンドの例のように、メトロもまた短命な、しかし星の一閃のごとき儚くも巧妙な音楽的理知を尖らせたバンドであった。実は今、初めて通して最後まで聞いている。当てがはずれ、更にはこの当時フォーク勢に偏狭な敵意を抱いていた事情から、初めの1分で停止してしまったのである。本当はエレクトリックプルーンズかトロッグズといった、サイケガレージについていま少し深める予定であったが、サイケサイケと自分でも五月蝿く感じ始めたので、当てずっぽうで手に取った紙ジャケCDなのである。
それにしても、何かそれについて書かねばならないという強制の中で改めてじっくり聞くと、今となっては浸みるものがある。世界各地に民族歌謡はあるが、その多くが祭りで人を煽るかどこか晴れがましく喜びを歌い上げるか、あるいは情念を慟哭するかではなかろうか。しかし英国あるいはアイルランドフォークの、基本的に元気を否定しつくした、あるいは否定と言う元気からそっと逃れるようにして侘び枯れた、低調な、寂しい繊細な感じは、単に英国だから、アイルランドだから、では済ますべきではなかろう、なぜなら良くも悪くもロックの血の3割ぐらいには成りえたのだから。いかんせんジョイスとベケットの国々なのである。油断はならない。少なくとも、70年代日本フォークのような、音楽的政治的厚かましさの薄汚さ、朴訥を装った狡猾、権力の犬に過ぎぬ誇りの無い野蛮さは、英国フォークには無いだろう。近々、吉田拓郎、松山千春、泉谷しげる、岡林信康ら、特に吉田拓郎を、彼がジャニーズのキンキキッズと関わり出した事に端を発した歴史的事件を掘り出すことで全否定批判する予定である。今しばらくお待ちあれ。なお、このアルバムをこうして聞くと、ドノヴァンは言うに及ばず、ブライアン・ウイルソンもヴァン・ダイク・パークスも唐突に噴火したのではなかった事が分かる。いずれのナンバーも、出来損ないの、田舎くさい賛美歌のように聞こえるが、本当はその逆なのだろう、賛美歌が、キリストをイコンとしたヨーロッパ民族のポップスなのである。8番目の、オン・ザ・ボムサイドはアレンジが少し凝ってて、サイケに吸収される以前のソフトロックの佳曲である。

さて、日曜日午前1時過ぎ、犬のように酒を舐めながら、音は消してカウントダウンTVを血走った眼でねめつけるようにして漫然と憤然と見続けるのは、人生における軽薄なる退廃の極みであろう。取り返しのつかぬ無駄な時間である。嘆いても後の祭りであった。たとえ猪口が備前、徳利も備前(義父の御手製)、酒も備前の、雄町の泉、であっても。
さておき、ダンカン・ブラウンである。英国。7年前ぐらいだろうか、そのジャケットからプログレだろうと思って購入した、いわゆるジャケ買いであるが、中味はクラシカルな英国フォーク、トラッドを色濃く基調にした物寂しいポップ作品であった。ギターがポロポロ鳴り、おとなしげな男が小さく呟いている。全く情報を得てない中で買ったものであるが、この人物、70年代終りの英国モダンポップ期においてロキシーミュージックや10CC、XTCといった奇怪なバンドに比肩し得た、メトロというデュオバンドの片割れであった。当時の、短命をよしとしたパンクバンドの例のように、メトロもまた短命な、しかし星の一閃のごとき儚くも巧妙な音楽的理知を尖らせたバンドであった。実は今、初めて通して最後まで聞いている。当てがはずれ、更にはこの当時フォーク勢に偏狭な敵意を抱いていた事情から、初めの1分で停止してしまったのである。本当はエレクトリックプルーンズかトロッグズといった、サイケガレージについていま少し深める予定であったが、サイケサイケと自分でも五月蝿く感じ始めたので、当てずっぽうで手に取った紙ジャケCDなのである。
それにしても、何かそれについて書かねばならないという強制の中で改めてじっくり聞くと、今となっては浸みるものがある。世界各地に民族歌謡はあるが、その多くが祭りで人を煽るかどこか晴れがましく喜びを歌い上げるか、あるいは情念を慟哭するかではなかろうか。しかし英国あるいはアイルランドフォークの、基本的に元気を否定しつくした、あるいは否定と言う元気からそっと逃れるようにして侘び枯れた、低調な、寂しい繊細な感じは、単に英国だから、アイルランドだから、では済ますべきではなかろう、なぜなら良くも悪くもロックの血の3割ぐらいには成りえたのだから。いかんせんジョイスとベケットの国々なのである。油断はならない。少なくとも、70年代日本フォークのような、音楽的政治的厚かましさの薄汚さ、朴訥を装った狡猾、権力の犬に過ぎぬ誇りの無い野蛮さは、英国フォークには無いだろう。近々、吉田拓郎、松山千春、泉谷しげる、岡林信康ら、特に吉田拓郎を、彼がジャニーズのキンキキッズと関わり出した事に端を発した歴史的事件を掘り出すことで全否定批判する予定である。今しばらくお待ちあれ。なお、このアルバムをこうして聞くと、ドノヴァンは言うに及ばず、ブライアン・ウイルソンもヴァン・ダイク・パークスも唐突に噴火したのではなかった事が分かる。いずれのナンバーも、出来損ないの、田舎くさい賛美歌のように聞こえるが、本当はその逆なのだろう、賛美歌が、キリストをイコンとしたヨーロッパ民族のポップスなのである。8番目の、オン・ザ・ボムサイドはアレンジが少し凝ってて、サイケに吸収される以前のソフトロックの佳曲である。
「ジゲンオルガン/ライブ@岡山ペパーランド(2008.11.23)」 2008年12月28日先勝 無雨
けたたましくもマスコミュニティは派遣切り派遣切りと鬼の首を取ったような正義づらの魯鈍な傲慢顔で書き立て喚きたてる年の瀬である。バブル後の好景気初期に勝ち組負け組と無遠慮に喧伝した舌の根の乾かぬうちの、言われた者の痛みを一慮せぬ言葉の卑劣をもてあそぶ無神経が、いっそ総括すれば今日の謂われ無き自然状態(ホッブズ)即ち資本主義を非科学的に制度化しているのである。ダーウィンの「種の起源」そして種の起源の資本側による功利的曲解に耐えかねて彼が世に問うた「人間の起源」からホッブズを批判したのちに資本主義批判したいところだが本題がまたしても遠のくのでまた今度。要約すれば、ダーウィンは人間の原始における相互扶助社会を証明しようとしており、生存競争はあくまでも他種属どうし、あるいは生物対環境での有り様だとしているのである。
さて、クリスマス・イヴだというのにテレビでタケシが東条英機に扮した戦時ドラマをやっていた。その意気やよし。明治憲法であっても、天皇裕仁の戦争責任は明白である。よって国民主権の司法によって有罪とされなければならない。国民主権の無い明治憲法下で許容されていた政治判断を、後の日本国憲法下で裁けるかは罪刑法定主義の問題となるかもしれぬが、もっと言えばそれは罪刑法定主義上の問題に過ぎない。なぜならば、主権在民は人民の形式であり原理であるからである。主権は革命によって封建領主から獲得された発見物ではない。原始だろうが中世封建社会だろうが近代市民社会だろうが、歴史の責任は人民にある。たとえ世襲領主であろうとも、本性として一斉蜂起革命権(ゼネスト権)を有する人民がそれを許容する以上(ゼネストしない以上)、領主は人民に選ばれていたのである。主権在民は歴史の原理である。歴史とは民主主義である。したがって、天皇が悪い、東条が悪い、近衛が悪い、辻が悪い、武藤が悪い、松岡が悪いと述べ立てたところで、政治の失政の責任は国民にある。そして失政の被害を最も蒙るのも国民ではなかったか。
翌日クリスマス日に、他番組は面白おかしい番組であったのに、どこかのテレビ局が「東京大空襲」という映画をやっていた。その意気やよし。当代一の女優、堀北マキの面影に釘付けになりつつ、当然ながら物申したい内容であるが、これもまた今度に。
さて、ジゲンオルガンの続きを。英国ドリーミングサイケポップバンドのカレードスコープなぞを聞きながら書いているため、文字書きによる覚醒のままドリームに逝ってしまいそうなので結論を急ぐ。音楽における奏者と聴衆の定在に対する異議申し立ては、演劇同様に近代の産物であったろう。演劇では演者が街に繰り出すことで世界を劇場にしようとしたり、あるいは演者が市井の会話のようにぼそぼそ会話する事でこうした二元論を打破しようとしたが、音楽でも同様に環境音の発見から主客未分を問うた。言うまでも無いだろう、ケージの3分44秒(正確な時間は忘れてしまった)は、挑発的に舞台に置かれたピアノをまともに奏することなく(確かピアノの蓋を開け閉めしたり、たまに鍵盤を一音叩いたりしているだけだったと思う)聴衆の発する物音に注意を向けさせ、主客区別せぬ奏者の創出あるいは音を出す者イコール音を聴く者、という有り様を提案したのであった。ただ、こうしたいわゆる観客参加型芸能は現在、インターネット社会の発達も相俟って多大な功罪も齎しているようである。現代美術でありがちな観客参加型企画の多くが詰まらぬものだし、リニューアルした「日立 世界不思議発見」での視聴者の解答を求めるための解答選択制が精妙なる番組の流れに馴染まぬ中だるみを起こし、且つは野々村まことのナイスボケの可能性を狭める愚行であり番組の魅力を半減するものだとは、当のジゲンオルガンのドラマーの弁であったと小生記憶する。
なお、舞台制批判においては、演劇分野においてスクリーンという科学装置を介在させる映画の出現と同様に、音楽でのレコードの発明が一役買っているだろう。生の演者奏者と客との間にスクリーンないしはレコードを介在させることで、それは読書に近くなる。こうした介在が、奏者と客との直接を否定し、作品と読者の対峙、あるいは物化した作品性が生じたのである。無論生の奏者とて作品と見なせ無くは無く、また作品の質をライブとレコードの違いで問うような事に当然意味は無かった。両者は位相が異なるだけであり、それぞれ別種の作品世界を持つに至ったのである。結局何が言いたいのか分からぬ韜晦に陥ってしまったが、それもよかろう、いずれにせよ、共産主義を批判する者は共産主義的思考しかできないくらい共産主義にのめり込む、あるいはファシズムを批判する者はファシストに自らならなければ当の批判対象を突破出来ぬ、即ち批評的立場に立って保身しながら言辞連ねても駄目だとこの頃思うようになったに付け、関が原で敵中突破しながら薩摩に帰った鬼島津を思う。ミイラ取りがミイラになった後の人間への復活にこそ新しい批評ないしは芸事が生まれるのである。
さて、ジゲンオルガンはロックの王道である。正確には、王道になりそうな飛び石の一つである。真面目な仕事をするバンドである。王道を見定めようとせぬ、横着且つ卑猥で奇妙で不真面目で時として資本におもねながらも人望は無い道こそ、逆説的にロックの王道となっている現在までの王道なきロック史、と結論づけていた小生であるが、なるほどここまで仕事が真面目であるとさらに倒錯的にロックらしからぬという意味でロックであった。ジゲンオルガンは凡庸ですらある異端である。ここで言うロックの横着とは、過去のロック音源を聞いて当然導かれるであろう次代のロックを奏しようとせぬ、単なる不勉強が原因なのか相当のアマノジャクがなせる技なのか分からぬ結果的怠慢を言う。人間皆違うといいながらも大抵考える事は似たり寄ったりである。そうした意味でごく普通の感性の持ち主が至極普通にロックに魅かれロックを過去の創世期から順に聴いていったならば、そして自らでもロックしたいと熱望したならば、次やるならば当然このあたりだろうな、とロック史の正統系譜上の予想は付くだろう。このあたり、というのを誰もやっていない、あるいはごく少数で系譜に連なるほどの隆盛ではないから王道なきロック史なのである。件の正統系譜が仮想のまま宙吊りになっているから王道不在といわれる由縁である。そして小生は王道不在を肯定する者であるが、特に在っても良いとも考える。
振り返るのも最早煩わしいが大局としてブルースやソウル、R&Bやフォーク等の合流であるロックは、その過程でアメリカで、白人的なるものと、母なるアフリカの土俗やアメリカ先住民の土俗と習合しながら(ブードゥー教やモルモン教)、時にアメリカ大陸同様に起きたカリブ海諸国での先住民と白人との習合土俗とのフィードバックを築きながら、その侵略性に無自覚な白人が開拓民としての土俗という珍妙な、矛盾した野蛮を野蛮なまま音楽にしていった最たるものがサイケデリアであった。これは全く新しかった。ロックを志すものならばこうしたサイケの本質に軸足を置くだろう。そして、より凶暴に激しく、即ちハードネスを切望して止まぬ。サイケの平和が静謐で薄らトンカチな欠伸から只ならぬ悪臭を吐きながら、聴く者の背骨ごと煽る、土と足裏との絶え間なき咬合である土俗のリズムは、民族に対して優しい祭りの興奮の安泰をも遠ざける白人の身勝手な狂気も乱入するものだから、人に優しくない凶暴を呈して、即ちリフという潔い思想に至るのはブルースのおかげでもある不思議。健康な人に心臓マッサージを施す無謀なおせっかいである。
そうしたサイケとハードの両輪によるガレージの爆走が米英でフラワーしながらザ・フーやレッドツェッペリンにまで至ったところで、プログレやメタルへと伸びて行った。このそれぞれはまた大きい潮流であるので一言では言い切れぬが、有色人種白色人種の習合土俗という面白いバランスだったところが、白人的文化が勝る形で変形していったのである。シンフォニックな構成あるいはジャズ的な奏法の取り入れなどは、サイケの発生と比べるならばロックの怒号を薄めこそすれ、さほど新しくも無い消化試合の呈に近いのである(個別のバンドを聞くと一概には言えぬが)。これはこれで楽しめはするが、これからやる音楽ではない、構築美の旧態に過ぎぬだろう。これへの反発としてパンクが生じたが、サイケの、かような歴史の忸怩をあえて知ろうともせぬ明朗なる無知のケツの青い戦略的宣言もまた、特に新しくも無く小生を白けさせるにしくはない。リズムのツッパリが白人的に過ぎる表のリズムのみに終始することが多く、これはこれで興味深いがこれ以上やっても仕方なかろう。明るい表の音楽には興味が持てない。何だか、俺はこういう音楽を聴きたいんだと言っているだけのようだが、ここで、哲学など趣味の言い訳に過ぎぬと言ってのけたニーチェを引用するのは怠慢だろうか。
さて、プログレもメタルもパンクも今更出来ぬとあればどうするか。近年流行の、パンキッシュな思想に彩られたサイコビリーなぞに未来は無い。黒人の裏のリズムもわきまえた芸達者であろうとも、それがわざわいしてグチャグチャ感が足りぬ整合性に安住しており、上っ面のサイケ臭なぞ小上手いだけで煩わしく、混沌に遊ぶいかがわしさに欠ける、物分りのいい就活野郎の上品ゆえに下品な音楽なのである。ではどうするか。凡庸なるロッカーがやるべき事は何なのか。いわゆるロックの代名詞でいながら、そのことがロックにとって漠然とした方向性でしかなくなっているハードロックを、即ちロックの王道を行くしかなかろう。そのためには、曖昧でいながら最もロックであったハードロックが至ってしまったプログレやメタルといった様式化を拒む必要があり、そのためには、サイケ=ガレージに踏ん張りながら踏み止まることが肝要である。そして、愚直にもその凶暴を今までに無く強化する事である。するとハードへと自然するだろう。こうした、サイケ=ガレージ=ハードロックが渾然となったロックにはツェッペリンがようやく到達して以降、ディープパープルはぎりぎり許容範囲とするとそれ以降、筋肉質の様式化へと固まり前期メタルの様相となるのであった。従ってかようなロックの王道(中道)は継承性を持たぬままいまだ不在である。(系譜にならぬという意味で不在は点在に等しい。)今ロックするならこの辺りである。そして、それをやろうというのが他ならぬジゲンオルガンであった。至極当然な思考の流れであり、凡庸である。しかし、実際にやっているあるいはやっていた人が少ないという詰まらぬ理由で、異端である。その優しさに縋りたくなるファンク的黒人的民族的安住を避けながらノリも大切にしながら捨て鉢な勢いでリズムの土俗をより凶暴せしめ、どもりを高い声低い声で奇声しながら、リフに身を委ねる浅知恵に頓着せぬ怒涛でひたぶるに煽りに煽り、けだしカラッとうるさい平和でもあるし、聴いてるとむかつくだけの小さい嫌がらせ、粘着質の陰湿、いっそ楽しくなくても良い内向であれ、と、ここに至って、ジゲンオルガンの実際の音楽性と小生の飽くなき熱望が混ざってしまったが、こうしたことを言わしむる音楽を提供したのがジゲンオルガンであった事は事実である。ジゲンオルガンはもう、英国的あるいは日本のGS的あるいは俳諧的とぼけ風味を加える余裕すらも捨て去って、専らロックが要請する性急さを厭わぬほどの野卑のリズム一筋に憑依されるべきである。GS的なるものについては今後きちんと論じなければならないが、日本人がやるロックとしてのGS風の加味は世界的に見て大きい特徴でも有るし、客には嬉しいおまけかもしれぬが、どうしても日の本の高雅な金満町人文化が匂うのでサイケの土着性の足手纏いになりかねぬ。それに、既にいくつかのバンドがやっている事でもあるし取り立てて新しくは無いという理由もある。キーボードとベースとドラムという編成も、うるささとリフとリズムのトリニティを成すに最小限であることはどこまでも本質的であらざるをえない。これから実地で成されるであろういま少しの修練により、ドラムは黒人の裏のリズムを会得するだろう、そしてそれを吹っ切ってまでも、ロックの不逞を奏するであろう。ロシア・フォルマニズムの詩人マヤコフスキーに「ズボンをはいた雲」という詩があるが、ズボンをはいた鬼であれ、角の無い鬼人であれ。
既に派を立てたという意味で立派なるロックをこの世に発信し始めたジゲンオルガンの音楽性について小生如きが提案すべくも無いので、音楽とは関係ない提言をささやかながらさせていただきたく。
1.失明せよ。音楽に光は要らない。照明を落とすか、客に目を閉じるよう強要せよ。
2.お好みのサイケシャツの上に、蓑(みの)を羽織るべし。烏帽子も被ればなお良し。草かんむりに衰えると書くとは、何と野趣溢れる字であろうか。
3.自身のロックに乗せて、日の本の古典を歌ってはいかがか。「へうげもの」の山田先生の初期の漫画に、方丈記の冒頭を明るく歌う村娘の話があるが、そこから創意を得ました。お勧めは、方丈記、平家物語、古今和歌集、新古今和歌集、和漢朗詠集、そして定番の梁塵秘抄といったところか。
追伸 ジゲンオルガンの創意なのか、どこぞの気の利いた贔屓客の押し付けなのか分からぬが、バスドラムにしつらえられた、真っ赤に熟れたほおずきが初めのフットペダルの一撃で落実したのが奇しくも晩秋のライブの始まりを告げ、終わりに、同じくバスドラムに施された正月飾りが、冷静に暴れ狂うベーシストの手で天空に舞い上げられたのは、2月のとんど祭りの見立てともなり、よかった。季節は先取りしてこそ、である。
ゆえあって脱藩するので、来週1月4日(日)は休載します。新年は1月11日(日)から会いましょう。よいお年を。
さて、クリスマス・イヴだというのにテレビでタケシが東条英機に扮した戦時ドラマをやっていた。その意気やよし。明治憲法であっても、天皇裕仁の戦争責任は明白である。よって国民主権の司法によって有罪とされなければならない。国民主権の無い明治憲法下で許容されていた政治判断を、後の日本国憲法下で裁けるかは罪刑法定主義の問題となるかもしれぬが、もっと言えばそれは罪刑法定主義上の問題に過ぎない。なぜならば、主権在民は人民の形式であり原理であるからである。主権は革命によって封建領主から獲得された発見物ではない。原始だろうが中世封建社会だろうが近代市民社会だろうが、歴史の責任は人民にある。たとえ世襲領主であろうとも、本性として一斉蜂起革命権(ゼネスト権)を有する人民がそれを許容する以上(ゼネストしない以上)、領主は人民に選ばれていたのである。主権在民は歴史の原理である。歴史とは民主主義である。したがって、天皇が悪い、東条が悪い、近衛が悪い、辻が悪い、武藤が悪い、松岡が悪いと述べ立てたところで、政治の失政の責任は国民にある。そして失政の被害を最も蒙るのも国民ではなかったか。
翌日クリスマス日に、他番組は面白おかしい番組であったのに、どこかのテレビ局が「東京大空襲」という映画をやっていた。その意気やよし。当代一の女優、堀北マキの面影に釘付けになりつつ、当然ながら物申したい内容であるが、これもまた今度に。
さて、ジゲンオルガンの続きを。英国ドリーミングサイケポップバンドのカレードスコープなぞを聞きながら書いているため、文字書きによる覚醒のままドリームに逝ってしまいそうなので結論を急ぐ。音楽における奏者と聴衆の定在に対する異議申し立ては、演劇同様に近代の産物であったろう。演劇では演者が街に繰り出すことで世界を劇場にしようとしたり、あるいは演者が市井の会話のようにぼそぼそ会話する事でこうした二元論を打破しようとしたが、音楽でも同様に環境音の発見から主客未分を問うた。言うまでも無いだろう、ケージの3分44秒(正確な時間は忘れてしまった)は、挑発的に舞台に置かれたピアノをまともに奏することなく(確かピアノの蓋を開け閉めしたり、たまに鍵盤を一音叩いたりしているだけだったと思う)聴衆の発する物音に注意を向けさせ、主客区別せぬ奏者の創出あるいは音を出す者イコール音を聴く者、という有り様を提案したのであった。ただ、こうしたいわゆる観客参加型芸能は現在、インターネット社会の発達も相俟って多大な功罪も齎しているようである。現代美術でありがちな観客参加型企画の多くが詰まらぬものだし、リニューアルした「日立 世界不思議発見」での視聴者の解答を求めるための解答選択制が精妙なる番組の流れに馴染まぬ中だるみを起こし、且つは野々村まことのナイスボケの可能性を狭める愚行であり番組の魅力を半減するものだとは、当のジゲンオルガンのドラマーの弁であったと小生記憶する。
なお、舞台制批判においては、演劇分野においてスクリーンという科学装置を介在させる映画の出現と同様に、音楽でのレコードの発明が一役買っているだろう。生の演者奏者と客との間にスクリーンないしはレコードを介在させることで、それは読書に近くなる。こうした介在が、奏者と客との直接を否定し、作品と読者の対峙、あるいは物化した作品性が生じたのである。無論生の奏者とて作品と見なせ無くは無く、また作品の質をライブとレコードの違いで問うような事に当然意味は無かった。両者は位相が異なるだけであり、それぞれ別種の作品世界を持つに至ったのである。結局何が言いたいのか分からぬ韜晦に陥ってしまったが、それもよかろう、いずれにせよ、共産主義を批判する者は共産主義的思考しかできないくらい共産主義にのめり込む、あるいはファシズムを批判する者はファシストに自らならなければ当の批判対象を突破出来ぬ、即ち批評的立場に立って保身しながら言辞連ねても駄目だとこの頃思うようになったに付け、関が原で敵中突破しながら薩摩に帰った鬼島津を思う。ミイラ取りがミイラになった後の人間への復活にこそ新しい批評ないしは芸事が生まれるのである。
さて、ジゲンオルガンはロックの王道である。正確には、王道になりそうな飛び石の一つである。真面目な仕事をするバンドである。王道を見定めようとせぬ、横着且つ卑猥で奇妙で不真面目で時として資本におもねながらも人望は無い道こそ、逆説的にロックの王道となっている現在までの王道なきロック史、と結論づけていた小生であるが、なるほどここまで仕事が真面目であるとさらに倒錯的にロックらしからぬという意味でロックであった。ジゲンオルガンは凡庸ですらある異端である。ここで言うロックの横着とは、過去のロック音源を聞いて当然導かれるであろう次代のロックを奏しようとせぬ、単なる不勉強が原因なのか相当のアマノジャクがなせる技なのか分からぬ結果的怠慢を言う。人間皆違うといいながらも大抵考える事は似たり寄ったりである。そうした意味でごく普通の感性の持ち主が至極普通にロックに魅かれロックを過去の創世期から順に聴いていったならば、そして自らでもロックしたいと熱望したならば、次やるならば当然このあたりだろうな、とロック史の正統系譜上の予想は付くだろう。このあたり、というのを誰もやっていない、あるいはごく少数で系譜に連なるほどの隆盛ではないから王道なきロック史なのである。件の正統系譜が仮想のまま宙吊りになっているから王道不在といわれる由縁である。そして小生は王道不在を肯定する者であるが、特に在っても良いとも考える。
振り返るのも最早煩わしいが大局としてブルースやソウル、R&Bやフォーク等の合流であるロックは、その過程でアメリカで、白人的なるものと、母なるアフリカの土俗やアメリカ先住民の土俗と習合しながら(ブードゥー教やモルモン教)、時にアメリカ大陸同様に起きたカリブ海諸国での先住民と白人との習合土俗とのフィードバックを築きながら、その侵略性に無自覚な白人が開拓民としての土俗という珍妙な、矛盾した野蛮を野蛮なまま音楽にしていった最たるものがサイケデリアであった。これは全く新しかった。ロックを志すものならばこうしたサイケの本質に軸足を置くだろう。そして、より凶暴に激しく、即ちハードネスを切望して止まぬ。サイケの平和が静謐で薄らトンカチな欠伸から只ならぬ悪臭を吐きながら、聴く者の背骨ごと煽る、土と足裏との絶え間なき咬合である土俗のリズムは、民族に対して優しい祭りの興奮の安泰をも遠ざける白人の身勝手な狂気も乱入するものだから、人に優しくない凶暴を呈して、即ちリフという潔い思想に至るのはブルースのおかげでもある不思議。健康な人に心臓マッサージを施す無謀なおせっかいである。
そうしたサイケとハードの両輪によるガレージの爆走が米英でフラワーしながらザ・フーやレッドツェッペリンにまで至ったところで、プログレやメタルへと伸びて行った。このそれぞれはまた大きい潮流であるので一言では言い切れぬが、有色人種白色人種の習合土俗という面白いバランスだったところが、白人的文化が勝る形で変形していったのである。シンフォニックな構成あるいはジャズ的な奏法の取り入れなどは、サイケの発生と比べるならばロックの怒号を薄めこそすれ、さほど新しくも無い消化試合の呈に近いのである(個別のバンドを聞くと一概には言えぬが)。これはこれで楽しめはするが、これからやる音楽ではない、構築美の旧態に過ぎぬだろう。これへの反発としてパンクが生じたが、サイケの、かような歴史の忸怩をあえて知ろうともせぬ明朗なる無知のケツの青い戦略的宣言もまた、特に新しくも無く小生を白けさせるにしくはない。リズムのツッパリが白人的に過ぎる表のリズムのみに終始することが多く、これはこれで興味深いがこれ以上やっても仕方なかろう。明るい表の音楽には興味が持てない。何だか、俺はこういう音楽を聴きたいんだと言っているだけのようだが、ここで、哲学など趣味の言い訳に過ぎぬと言ってのけたニーチェを引用するのは怠慢だろうか。
さて、プログレもメタルもパンクも今更出来ぬとあればどうするか。近年流行の、パンキッシュな思想に彩られたサイコビリーなぞに未来は無い。黒人の裏のリズムもわきまえた芸達者であろうとも、それがわざわいしてグチャグチャ感が足りぬ整合性に安住しており、上っ面のサイケ臭なぞ小上手いだけで煩わしく、混沌に遊ぶいかがわしさに欠ける、物分りのいい就活野郎の上品ゆえに下品な音楽なのである。ではどうするか。凡庸なるロッカーがやるべき事は何なのか。いわゆるロックの代名詞でいながら、そのことがロックにとって漠然とした方向性でしかなくなっているハードロックを、即ちロックの王道を行くしかなかろう。そのためには、曖昧でいながら最もロックであったハードロックが至ってしまったプログレやメタルといった様式化を拒む必要があり、そのためには、サイケ=ガレージに踏ん張りながら踏み止まることが肝要である。そして、愚直にもその凶暴を今までに無く強化する事である。するとハードへと自然するだろう。こうした、サイケ=ガレージ=ハードロックが渾然となったロックにはツェッペリンがようやく到達して以降、ディープパープルはぎりぎり許容範囲とするとそれ以降、筋肉質の様式化へと固まり前期メタルの様相となるのであった。従ってかようなロックの王道(中道)は継承性を持たぬままいまだ不在である。(系譜にならぬという意味で不在は点在に等しい。)今ロックするならこの辺りである。そして、それをやろうというのが他ならぬジゲンオルガンであった。至極当然な思考の流れであり、凡庸である。しかし、実際にやっているあるいはやっていた人が少ないという詰まらぬ理由で、異端である。その優しさに縋りたくなるファンク的黒人的民族的安住を避けながらノリも大切にしながら捨て鉢な勢いでリズムの土俗をより凶暴せしめ、どもりを高い声低い声で奇声しながら、リフに身を委ねる浅知恵に頓着せぬ怒涛でひたぶるに煽りに煽り、けだしカラッとうるさい平和でもあるし、聴いてるとむかつくだけの小さい嫌がらせ、粘着質の陰湿、いっそ楽しくなくても良い内向であれ、と、ここに至って、ジゲンオルガンの実際の音楽性と小生の飽くなき熱望が混ざってしまったが、こうしたことを言わしむる音楽を提供したのがジゲンオルガンであった事は事実である。ジゲンオルガンはもう、英国的あるいは日本のGS的あるいは俳諧的とぼけ風味を加える余裕すらも捨て去って、専らロックが要請する性急さを厭わぬほどの野卑のリズム一筋に憑依されるべきである。GS的なるものについては今後きちんと論じなければならないが、日本人がやるロックとしてのGS風の加味は世界的に見て大きい特徴でも有るし、客には嬉しいおまけかもしれぬが、どうしても日の本の高雅な金満町人文化が匂うのでサイケの土着性の足手纏いになりかねぬ。それに、既にいくつかのバンドがやっている事でもあるし取り立てて新しくは無いという理由もある。キーボードとベースとドラムという編成も、うるささとリフとリズムのトリニティを成すに最小限であることはどこまでも本質的であらざるをえない。これから実地で成されるであろういま少しの修練により、ドラムは黒人の裏のリズムを会得するだろう、そしてそれを吹っ切ってまでも、ロックの不逞を奏するであろう。ロシア・フォルマニズムの詩人マヤコフスキーに「ズボンをはいた雲」という詩があるが、ズボンをはいた鬼であれ、角の無い鬼人であれ。
既に派を立てたという意味で立派なるロックをこの世に発信し始めたジゲンオルガンの音楽性について小生如きが提案すべくも無いので、音楽とは関係ない提言をささやかながらさせていただきたく。
1.失明せよ。音楽に光は要らない。照明を落とすか、客に目を閉じるよう強要せよ。
2.お好みのサイケシャツの上に、蓑(みの)を羽織るべし。烏帽子も被ればなお良し。草かんむりに衰えると書くとは、何と野趣溢れる字であろうか。
3.自身のロックに乗せて、日の本の古典を歌ってはいかがか。「へうげもの」の山田先生の初期の漫画に、方丈記の冒頭を明るく歌う村娘の話があるが、そこから創意を得ました。お勧めは、方丈記、平家物語、古今和歌集、新古今和歌集、和漢朗詠集、そして定番の梁塵秘抄といったところか。
追伸 ジゲンオルガンの創意なのか、どこぞの気の利いた贔屓客の押し付けなのか分からぬが、バスドラムにしつらえられた、真っ赤に熟れたほおずきが初めのフットペダルの一撃で落実したのが奇しくも晩秋のライブの始まりを告げ、終わりに、同じくバスドラムに施された正月飾りが、冷静に暴れ狂うベーシストの手で天空に舞い上げられたのは、2月のとんど祭りの見立てともなり、よかった。季節は先取りしてこそ、である。
ゆえあって脱藩するので、来週1月4日(日)は休載します。新年は1月11日(日)から会いましょう。よいお年を。
「ジゲンオルガン/ライブ@岡山ペパーランド(2008.11.23)」 2008年12月21日 仏滅 冬至悲雨
最近は、酸化防止剤(亜硫酸塩)無添加の国産ワインを好飲している。ワインの銘柄や味の差異にさほど詳しくもうるさくもない小生であるが、景気付けのため手頃な価格のワインを飲むに付け、二日酔いとまでは行かないけれどもやはり翌日に残る、と言う日常にさしたる疑問が無いはずが無く、一般にワイン中のタンニンが日本人の臓器にとって処理困難ゆえに胃や胸のむかつきが残ると言われても納得していなかった。
個人的な経験則に過ぎぬが300円から600円の廉価ワインは翌日のむかつきが酷く、価格が上がるにつれ酔い残り少なくなり、1000円~3000円だと我慢しうる程度のむかつきを翌日残すものの喉を通過したときの華麗なる濃旨淡旨ゆえ小生如きでも満足できるのであった。それ以上の価格のワイン世界は知らぬ。知らぬにしても、素人目にしてどうにも怪しく映るのが、含有成分表記されている酸化防止剤の存在であった。こやつが何もかもぶち壊しているのではなかろうか。常日頃頭の片隅にそう念じていた矢先、近所の詰まらぬスーパー(惣菜が激マズ)で、酸化防止剤無添加を大きく謳ったラベルの山梨ワインの赤を発見した。値は560円ほど。即買い、飲むに、おお旨い。酸化防止剤が無いためとは早急に考えられぬし一般に赤ワインには皮が入っているからあのシワイ苦味が伴うと言われる。そのシワイ苦味が赤ワインの旨味なんだと愚かしくも自己に言い聞かせていた。国産葡萄と西洋産葡萄の違いの影響も大きいと思われるが、兎も角喉にしつこく絡みつくシワイ感じが尖んがらず、且つ苦味とトロミが全的に転がるように醇乎たる旨味はどこまでもまろやかで濃厚かつ不透明な静まりが胃に沈下していく未分未明のようで、良い。ついつい煽りがちになるものの、翌日の寝覚めは誠にすっきりと、後腐れない爽快であった。
昨晩も調子に乗って無添加ワイン赤(件の山梨ワインとは別銘柄。)を喉に転がしながら、ブラタモリの放送をNHKで待っていた。その多趣味の一つとして古地図数寄のタモリが、江戸や明治の古地図を頼りに今の東京をぶらつくという企画。タモリ倶楽部から独立したような趣向ではあるが面白くないはずが無い。ただ、タモリ倶楽部同様に深夜1時くらいの番組ゆえ、その時間はたいてい酩酊しておる小生にとっては拝見難しく、結局見逃し睡眠。ただ、以前見たブラタモリ、表参道にて、興味をそそられたタモリが、自身が学生の頃からある山陽堂書店に入った折、山田先生の漫画「へうげもの」最新第7巻が画面の隅に捉えられたのを見逃す視聴者はおるまい。タモリ倶楽部やブラタモリを好む者ならば、へうげものを隔週読まぬ者はおるまいとばかりの、暗黙の符丁が顕在していた。少なくとも小生はそう感ぜられた。
朝起きればNHKの新日曜美術館。毎週見る。本日は佐伯ユウゾウ。結核を病みながらパリの下町をごりごり描き続けたイメージの強い画家であるが、本日のゲストは高橋源一郎。多くの文化人や学者ゲストが情緒的な感銘や瑣末な相槌しか入れぬが、源一郎氏、当然ながら1930年代の社会(主義)運動隆盛のパリを指摘、佐伯氏がしばしば描きながら見たであろう汚い壁の広告は政治的アジビラではなかったか、と卓見しながら、日本共産党設立との同時代性も指摘するに至っては、これまでの番組にそぐわぬ不穏な空気がスタジオに流れざるを得ぬ。無感覚のアナウンサーが事の重大を感ずる知性を見せぬままそれに対する無反応は致し方無いにしても、壇ふみが、画家最期の作の郵便配達員の絵の印象を、古里日本からの便りを持って来る郵便屋さん、などと解釈することで、源一郎がもたらす不穏な空気を情緒的に誤魔化そうとするも、しかし郵便屋の老人の目の暗く空ろな絶望は何なのか、と、矢張り不穏な空気を最後まで撒き散らす源一郎氏であり、良かった。
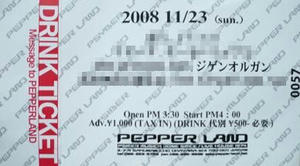
閑話休題、ジゲンオルガンである。日の本は鳥取産。2000年以降結成か。小生が聴いた時はベース兼キーボードとドラムの二人編成、主に中国地方でライブを中心としており、現在いまだに彼らのレコード音源は全国流通していない実情のため、小生もレコード音源は入手していない。従って一度聴いたライブ模様を中心に記録し、ささやかながら立派な出世の一助としたい。そう、音楽体験は笑いと共に記憶し難いゆえ、如何に印象強かろうとも詳細の音の仕組みが忘却に晒されつつある始末、いわんやジゲンオルガンの音楽性は、小生が私物する、たかだかではあるが千枚程度の音源を全て紹介し終えた後に導かれるであろう新しい未来性を孕むゆえ、今書く事は性急に過ぎるにしても、もったいぶられる結論などありはせぬ、隠し立てされぬ結論の、繰り返しも厭わぬ連打こそ重要必至と心得、既に朧ろの記憶を頼りに記録するしかないのである。よって忸怩たる思いをされるであろう曖昧な記述ご容赦願いたい。それほどの緊急的歴史的出世を要するほどの重要なバンドである。
さて、ライブというからには、音楽について語る前に舞台演芸の是非について批判せねばならなかった。ギリシャ悲劇、オペラ、オーケストラ、室内楽、ワーグナー楽劇やご当地神楽、人形浄瑠璃だの京劇だの民族音楽だのと個別に分析する必要も無いほど、舞台演芸ではいずれも、見る者見られる者問わずその演芸に集う集団が認知する舞台という場所が概念化されており、境界を成しながら見る者(聴く者)/見られる者(聴かれる者)あるいは行為される者/行為する者、の二分を定式化していた。この時点で既に退屈である。退屈には罪は無いが、この退屈さは破壊されなければならない。
主体と客体、言葉と対象、といった定形の安全への無自覚な連なりへの最たるものが舞台演芸であった。(以降、何も小生が拙い説明などしなくても物の分かった人士であるならば常識レベルのことをくどくどしく述べるのを容赦いただきたく。)こうした二元論を他者論の函数として考えると分かりやすいかもしれない。古来より、他者との関係性の下で自己が定立されてきたが、この際に関係性を能力化することで他者の他者性が軽んじられてきたのである。即ち、絶対的に関係性を持ち得ない他者が、である。こうした他者性に関して、ヘーゲルまではまだその他者性に踏み止まろうとする誠実な煩悶、迷いがあった。これまた当然のことながら、ヘーゲルの弁証法はテーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼへと至る単純な機械論ではない。それは彼の「精神現象学」での主張そして文体に見られる。あの、どこまでもテーゼとアンチテーゼの存在を認めながら、ジンテーゼには容易には至ろうとせぬ踏ん張る螺旋の文。ちなみに小生は「精神現象学」を小説だと考えている。文体論を否定しながら文体でしか何事も語れぬものが小説であるとするならば。(文体は何事も語らぬので小説は何事も語らぬ。)マルクスは彼のヘーゲル批判の中で、テーゼとアンチテーゼとの共犯関係、結局テーゼあってのアンチではないかと、ヘーゲルの他者性(アンチテーゼ)の不徹底を揶揄しているが、ヘーゲルにしてみれば、もっと俺の迷いを察してくれ、と言いたいところであろう。マルクス主義以降の、こうした他者性への無自覚はブランショやデリダ、ヴィトゲンシュタインらに改めて批判されても尚、現在蔓延っている。そして、一旦関係性の中で消化された他者は分類されキャラクタライズされながら、自ずと分類不能のものを差別化し、敵視化しかねず、もっと説明可能であるが極論すると全体主義に陥るだろう。芸術芸能に目的は無い。ただ、その時々に面白おかしければ良いのである。何事かを成す能力も無い。ただし、唯一目的として許されるならば、現にある全体主義への批判と破壊である。これ以外に無い。全体主義は予防するに限るが、予防は、これまた説明を省くが全体主義的概念に連なるので、従って、起きてしまった全体主義に対して、全力で戦わなければならないのが芸の道である。無論、全体主義の様相は多かれ少なかれ権力組織の常であるからして、芸人はその有形無形の作品でいついかなる時でも全体主義と戦わざるを得ぬ。
よって、舞台演芸の歴史的位置に思いをいたさぬ演者並びに客は、致命的に、その音楽を奏する乃至は聴く権利を失するのである。客の居る会場で音を出せば客が聴く、あるいは会場に行けば金を出せば音楽が聴ける、と意識せず思っているのであれば、音楽にとって不幸な事である。舞台演芸に関して言えば、予め全的に承認された大ホールで大声で大仰に演ずるのへの批判から、例えばロシア革命前後にて、街頭での、さながらそれが革命の実際ではなかったかと思われるほどの大規模な群集劇が演じられたし(当時、レーニンのそっくりさん俳優が数人居たようだ)、寺山修二の街頭劇や、平田オリザの、舞台の隅でぼそぼそ普通の音量で喋る演劇(大声発声練習演劇への痛烈批判)などによって、舞台性の定式化が批判されてきた。音楽では・・・(長くなったので今日はここで打ち切ります。来週、音楽分野での舞台性批判の例から始めて、結局舞台性批判とは関係ないが本論のジゲンオルガンの音楽性について語ります。続く。)
個人的な経験則に過ぎぬが300円から600円の廉価ワインは翌日のむかつきが酷く、価格が上がるにつれ酔い残り少なくなり、1000円~3000円だと我慢しうる程度のむかつきを翌日残すものの喉を通過したときの華麗なる濃旨淡旨ゆえ小生如きでも満足できるのであった。それ以上の価格のワイン世界は知らぬ。知らぬにしても、素人目にしてどうにも怪しく映るのが、含有成分表記されている酸化防止剤の存在であった。こやつが何もかもぶち壊しているのではなかろうか。常日頃頭の片隅にそう念じていた矢先、近所の詰まらぬスーパー(惣菜が激マズ)で、酸化防止剤無添加を大きく謳ったラベルの山梨ワインの赤を発見した。値は560円ほど。即買い、飲むに、おお旨い。酸化防止剤が無いためとは早急に考えられぬし一般に赤ワインには皮が入っているからあのシワイ苦味が伴うと言われる。そのシワイ苦味が赤ワインの旨味なんだと愚かしくも自己に言い聞かせていた。国産葡萄と西洋産葡萄の違いの影響も大きいと思われるが、兎も角喉にしつこく絡みつくシワイ感じが尖んがらず、且つ苦味とトロミが全的に転がるように醇乎たる旨味はどこまでもまろやかで濃厚かつ不透明な静まりが胃に沈下していく未分未明のようで、良い。ついつい煽りがちになるものの、翌日の寝覚めは誠にすっきりと、後腐れない爽快であった。
昨晩も調子に乗って無添加ワイン赤(件の山梨ワインとは別銘柄。)を喉に転がしながら、ブラタモリの放送をNHKで待っていた。その多趣味の一つとして古地図数寄のタモリが、江戸や明治の古地図を頼りに今の東京をぶらつくという企画。タモリ倶楽部から独立したような趣向ではあるが面白くないはずが無い。ただ、タモリ倶楽部同様に深夜1時くらいの番組ゆえ、その時間はたいてい酩酊しておる小生にとっては拝見難しく、結局見逃し睡眠。ただ、以前見たブラタモリ、表参道にて、興味をそそられたタモリが、自身が学生の頃からある山陽堂書店に入った折、山田先生の漫画「へうげもの」最新第7巻が画面の隅に捉えられたのを見逃す視聴者はおるまい。タモリ倶楽部やブラタモリを好む者ならば、へうげものを隔週読まぬ者はおるまいとばかりの、暗黙の符丁が顕在していた。少なくとも小生はそう感ぜられた。
朝起きればNHKの新日曜美術館。毎週見る。本日は佐伯ユウゾウ。結核を病みながらパリの下町をごりごり描き続けたイメージの強い画家であるが、本日のゲストは高橋源一郎。多くの文化人や学者ゲストが情緒的な感銘や瑣末な相槌しか入れぬが、源一郎氏、当然ながら1930年代の社会(主義)運動隆盛のパリを指摘、佐伯氏がしばしば描きながら見たであろう汚い壁の広告は政治的アジビラではなかったか、と卓見しながら、日本共産党設立との同時代性も指摘するに至っては、これまでの番組にそぐわぬ不穏な空気がスタジオに流れざるを得ぬ。無感覚のアナウンサーが事の重大を感ずる知性を見せぬままそれに対する無反応は致し方無いにしても、壇ふみが、画家最期の作の郵便配達員の絵の印象を、古里日本からの便りを持って来る郵便屋さん、などと解釈することで、源一郎がもたらす不穏な空気を情緒的に誤魔化そうとするも、しかし郵便屋の老人の目の暗く空ろな絶望は何なのか、と、矢張り不穏な空気を最後まで撒き散らす源一郎氏であり、良かった。
閑話休題、ジゲンオルガンである。日の本は鳥取産。2000年以降結成か。小生が聴いた時はベース兼キーボードとドラムの二人編成、主に中国地方でライブを中心としており、現在いまだに彼らのレコード音源は全国流通していない実情のため、小生もレコード音源は入手していない。従って一度聴いたライブ模様を中心に記録し、ささやかながら立派な出世の一助としたい。そう、音楽体験は笑いと共に記憶し難いゆえ、如何に印象強かろうとも詳細の音の仕組みが忘却に晒されつつある始末、いわんやジゲンオルガンの音楽性は、小生が私物する、たかだかではあるが千枚程度の音源を全て紹介し終えた後に導かれるであろう新しい未来性を孕むゆえ、今書く事は性急に過ぎるにしても、もったいぶられる結論などありはせぬ、隠し立てされぬ結論の、繰り返しも厭わぬ連打こそ重要必至と心得、既に朧ろの記憶を頼りに記録するしかないのである。よって忸怩たる思いをされるであろう曖昧な記述ご容赦願いたい。それほどの緊急的歴史的出世を要するほどの重要なバンドである。
さて、ライブというからには、音楽について語る前に舞台演芸の是非について批判せねばならなかった。ギリシャ悲劇、オペラ、オーケストラ、室内楽、ワーグナー楽劇やご当地神楽、人形浄瑠璃だの京劇だの民族音楽だのと個別に分析する必要も無いほど、舞台演芸ではいずれも、見る者見られる者問わずその演芸に集う集団が認知する舞台という場所が概念化されており、境界を成しながら見る者(聴く者)/見られる者(聴かれる者)あるいは行為される者/行為する者、の二分を定式化していた。この時点で既に退屈である。退屈には罪は無いが、この退屈さは破壊されなければならない。
主体と客体、言葉と対象、といった定形の安全への無自覚な連なりへの最たるものが舞台演芸であった。(以降、何も小生が拙い説明などしなくても物の分かった人士であるならば常識レベルのことをくどくどしく述べるのを容赦いただきたく。)こうした二元論を他者論の函数として考えると分かりやすいかもしれない。古来より、他者との関係性の下で自己が定立されてきたが、この際に関係性を能力化することで他者の他者性が軽んじられてきたのである。即ち、絶対的に関係性を持ち得ない他者が、である。こうした他者性に関して、ヘーゲルまではまだその他者性に踏み止まろうとする誠実な煩悶、迷いがあった。これまた当然のことながら、ヘーゲルの弁証法はテーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼへと至る単純な機械論ではない。それは彼の「精神現象学」での主張そして文体に見られる。あの、どこまでもテーゼとアンチテーゼの存在を認めながら、ジンテーゼには容易には至ろうとせぬ踏ん張る螺旋の文。ちなみに小生は「精神現象学」を小説だと考えている。文体論を否定しながら文体でしか何事も語れぬものが小説であるとするならば。(文体は何事も語らぬので小説は何事も語らぬ。)マルクスは彼のヘーゲル批判の中で、テーゼとアンチテーゼとの共犯関係、結局テーゼあってのアンチではないかと、ヘーゲルの他者性(アンチテーゼ)の不徹底を揶揄しているが、ヘーゲルにしてみれば、もっと俺の迷いを察してくれ、と言いたいところであろう。マルクス主義以降の、こうした他者性への無自覚はブランショやデリダ、ヴィトゲンシュタインらに改めて批判されても尚、現在蔓延っている。そして、一旦関係性の中で消化された他者は分類されキャラクタライズされながら、自ずと分類不能のものを差別化し、敵視化しかねず、もっと説明可能であるが極論すると全体主義に陥るだろう。芸術芸能に目的は無い。ただ、その時々に面白おかしければ良いのである。何事かを成す能力も無い。ただし、唯一目的として許されるならば、現にある全体主義への批判と破壊である。これ以外に無い。全体主義は予防するに限るが、予防は、これまた説明を省くが全体主義的概念に連なるので、従って、起きてしまった全体主義に対して、全力で戦わなければならないのが芸の道である。無論、全体主義の様相は多かれ少なかれ権力組織の常であるからして、芸人はその有形無形の作品でいついかなる時でも全体主義と戦わざるを得ぬ。
よって、舞台演芸の歴史的位置に思いをいたさぬ演者並びに客は、致命的に、その音楽を奏する乃至は聴く権利を失するのである。客の居る会場で音を出せば客が聴く、あるいは会場に行けば金を出せば音楽が聴ける、と意識せず思っているのであれば、音楽にとって不幸な事である。舞台演芸に関して言えば、予め全的に承認された大ホールで大声で大仰に演ずるのへの批判から、例えばロシア革命前後にて、街頭での、さながらそれが革命の実際ではなかったかと思われるほどの大規模な群集劇が演じられたし(当時、レーニンのそっくりさん俳優が数人居たようだ)、寺山修二の街頭劇や、平田オリザの、舞台の隅でぼそぼそ普通の音量で喋る演劇(大声発声練習演劇への痛烈批判)などによって、舞台性の定式化が批判されてきた。音楽では・・・(長くなったので今日はここで打ち切ります。来週、音楽分野での舞台性批判の例から始めて、結局舞台性批判とは関係ないが本論のジゲンオルガンの音楽性について語ります。続く。)
「count five/phychotic revelation(1966~1969)big beat cdwikd230」 2008年12月14日 先負 先春
さて、カウント・ファイブである。米国はカリフォルニア州サンホセ産。ジャケットなぞ見るとマザーズ オブ インベンションのフリークアウトライブの前座を努めており、チャートでもガレージ勢に珍しく首位を得たりと人気のバンドだったようである。本当はエレクトリックプルーンズの紹介を致したかったがコレを先に写真取りしてプロ愚に登録したものだから仕方ない気持ちである。ガレージとはいっても暗闇地獄で水子がしゃれこうべ肋骨ギターをかき鳴らす差し迫った怒りをずぼらに発散する風でも無く、育ちのいい学生さんがブリティッシュ勢に感銘してやり出した卒の無い健康ロックといってしまっては如何ともしがたいが、しかしそうはいっても聴くべき所にパンチを効かす気骨がガレージという出自に根差した黒い攻撃性をギラリとさせるに吝かでない。メタルとなると憎悪を叩き付け出すがこの頃はまだどこか陽性の怒りに留まっているのが好悪分かれるところであろう。先週挙げたミュージックマシーンでもそうであったが、ガレージの緊急的怒りがパファッと眠りに入る時、安らかなサイケデリアの不敵な夢が獰猛に炙り出される。如何に人気のR&Bガレージ学生バンドであろうともそうした音楽の宿命から免れ得ない誇りが固持されているのである。結局、ひたぶるにかっこいいバンドである。比べる必要など皆無であるが20年前からのコンビニ音楽の、こうした宿命をも負いきれぬほどの誇りの無さ、自縛する美意識の無さにはほとほと嫌気がさす。いや、むしろ、どこまでも資本と支持率におもねようとする自動的意識の強固が凄いのであろう、すなわち商魂である。下らないこと書いたので宿命云々は世迷言と思うてくだされ。ともあれ、ガレージもサイケもロックの様相を語る上で重要な概念であり且つ表裏を成すあらましである。また、目印のために、ブルースと、ブルースが片親とされがちなリズム&ブルースとの間に疑問のクサビを打ち込んでおいてまたの再会。
count five
john "sean" byrne:lead vocals, rhythm guitar
kenn ellner:lead vocals, harp, percussion
john "mouse" michalski:lead guitar
roy chaney:bass
craig "butch" atkinson:drum
「the music machine/the very best of the music machine turn on(1966)col-cd-6044」 2008年12月7日 友引 寒晴
広島県の木曜日23時半からは、テレビジョン史上の金字塔の一つである雨トークが放送される。雨トークについては他の方に譲るとして、今日はその雨トーク後の、ラブチェンという番組の感想を。普段のラブチェンは内容がいささかきつく、小生にとってもハードコアなゆえ、ほぼ見たことは無かった。夫婦交換バラエティーであるが、登場する夫婦の階級がいずれも地元ヤンキー(ジモヤン)、という荒みようは、相当の数寄者でないと楽しめない、きっつい夜を提供しようと言うのである。子沢山のジモヤン夫婦の夫は超清潔好き、他方のジモヤン夫婦の夫は飲んだくれ、という夫婦を交換したりする。交換の意味あるのか。こうして書くと面白いように思う小生ではある。ただし、12月4日はこれまでと違っていた。芸能人の、ホンコン、と、伊藤かずえ、という女優さんが2泊くらいする構成。無論かれらはそれぞれに配偶者を有している、40代半ばの中年である。ジモヤン夫婦のように些細な事をすさませる尖った事件など無く、回転寿司などつまんだり台所で共に料理作ったりしながら、取るに足らぬ会話、互いの夫婦生活の日常をぽつぽつ交わすのみである。それなりに人生を重ねた中年男女が擬似夫婦するのだから、程よく枯れて、程よく艶があるのは当然、そこを視聴者に味あわせる新しい試みであった。ホンコンと伊藤かずえ、という組み合わせも、何とも微妙で良い。土曜の午後の、詰め込み系旅番組の芸能人選択に匹敵する渋さである。ジモヤンに関しては、本ページがある「好評ゼロ」のトップページの「俺が見たジモヤン」を参照してくだされ!どしどし書き込みしてください。また、擬似恋愛番組史については、また宿題と言う事で。ネルトン→あいのり→恋するハニカミ→グータンヌーヴォ→ラブチェン。
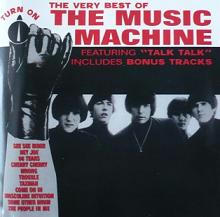 閑話休題、ミュージックマシーンである。米国はロス・エンジェルス産。メンバー全員が右手に黒革の手袋を装着する不敵な男たちの髪型は英国風マッシュルームカット。如何せん異様ではあるが、その音楽はロックに対していたって真面目である。ストーンズ的チンピラ風を律儀に継承する悪そうな歌唱はあくまでもやさぐれの渋さであるし、抑え気味のファズがかえって彼らのトンガリを増すギター、打つべきところを確実に打つドラム、ブザーのようにビービー鳴るだけのうるささかと思いきや、とぼけた風味も忘れぬ気ままなオルガン、唸ってなんぼの熱いベース、先走るマラカスが一丸となって臆面も無く迫ってくるのだから最高である。わが国で伝統工芸の国家的指定と援助を受けるには30件以上の同業者が同じ地域に住んでいなければならぬ条件があるようである。国家や世間や資本からの承認など糞くらえであるが、文化的一潮流の形成が更なる文化的質の向上変革に寄与するならば、たとえ凡庸であっても同じような事をやっている連中が多いにこしたことはないのかもしれない。このことは無論それが、良い音楽であることに限っての事ではある。したがって、ミュージックマシンの仕事は無茶苦茶突飛ではないという意味で凡庸ではあるが、ロックとロック数寄にとってはこの上ない貢献を果たした滋味あるバンドなのである。4曲目のタックスマンのカバー、6曲目のmasculine intuition(オリジナル)、8曲目のシー・シー・ライダー(マ・レイニーのカバー?)が秀逸。
閑話休題、ミュージックマシーンである。米国はロス・エンジェルス産。メンバー全員が右手に黒革の手袋を装着する不敵な男たちの髪型は英国風マッシュルームカット。如何せん異様ではあるが、その音楽はロックに対していたって真面目である。ストーンズ的チンピラ風を律儀に継承する悪そうな歌唱はあくまでもやさぐれの渋さであるし、抑え気味のファズがかえって彼らのトンガリを増すギター、打つべきところを確実に打つドラム、ブザーのようにビービー鳴るだけのうるささかと思いきや、とぼけた風味も忘れぬ気ままなオルガン、唸ってなんぼの熱いベース、先走るマラカスが一丸となって臆面も無く迫ってくるのだから最高である。わが国で伝統工芸の国家的指定と援助を受けるには30件以上の同業者が同じ地域に住んでいなければならぬ条件があるようである。国家や世間や資本からの承認など糞くらえであるが、文化的一潮流の形成が更なる文化的質の向上変革に寄与するならば、たとえ凡庸であっても同じような事をやっている連中が多いにこしたことはないのかもしれない。このことは無論それが、良い音楽であることに限っての事ではある。したがって、ミュージックマシンの仕事は無茶苦茶突飛ではないという意味で凡庸ではあるが、ロックとロック数寄にとってはこの上ない貢献を果たした滋味あるバンドなのである。4曲目のタックスマンのカバー、6曲目のmasculine intuition(オリジナル)、8曲目のシー・シー・ライダー(マ・レイニーのカバー?)が秀逸。
ああ、ロックにおけるリフという思想、というテーマとも、いずれ向き合う必要がある。
そうすると、どうして日の本の、巷で嫌でも耳にしてしまうコンビニ音楽、腐れヒップホップ歌謡、馴れ合いボーカルユニットや功利主義ダンスボーカルグループ私企業が、如何に絶対的に有害で誇りの無い卑しい音楽であるかを説明しなければならぬだろう。説明するのも本当は時間の無駄なほど絶望的に下らない上に、駆逐しなければならない必要性すらあるように思うのだが、きっちりやりたいのでまたの機会にしたい。ただ、最早、心あるバンドやリスナーがひたすら己が良い音楽に向かって精進するだけでは足りないのではないか、何らかの実力行使も辞さぬ思想が必要なのではないかとすら考えている。美学的唯物史観の誕生を思うが、その先の結末も何となく分るし、寂しい昼下がり。。
the music machine
sean bonniwell, rhythm guitar
mark landon, lead guitar
keith olsen, bass guitar
doug rhodes, organ
ああ、ロックにおけるリフという思想、というテーマとも、いずれ向き合う必要がある。
そうすると、どうして日の本の、巷で嫌でも耳にしてしまうコンビニ音楽、腐れヒップホップ歌謡、馴れ合いボーカルユニットや功利主義ダンスボーカルグループ私企業が、如何に絶対的に有害で誇りの無い卑しい音楽であるかを説明しなければならぬだろう。説明するのも本当は時間の無駄なほど絶望的に下らない上に、駆逐しなければならない必要性すらあるように思うのだが、きっちりやりたいのでまたの機会にしたい。ただ、最早、心あるバンドやリスナーがひたすら己が良い音楽に向かって精進するだけでは足りないのではないか、何らかの実力行使も辞さぬ思想が必要なのではないかとすら考えている。美学的唯物史観の誕生を思うが、その先の結末も何となく分るし、寂しい昼下がり。。
the music machine
sean bonniwell, rhythm guitar
mark landon, lead guitar
keith olsen, bass guitar
doug rhodes, organ

